16日、久しぶりに板橋の銀行へ行く用事があり出かけました。
用事を済ませ、約束の場所へと。
以前そこの支店長だった方の所、現在は不動産業をやっています。
とても見識のある方なので、機会があるたびに訪問します。
その日も、お伺いすることを電話で申し出ていたのです。
徒歩で20分ぐらいかかりますか、約束の時間に余裕があったので途中以前から気にかけていた神社へ向かうことにしました。
鳥居の脇にある石碑に氷川神社とありました。
周りは住宅地、建立された頃は広々としたところだったのでしょうが。
日本書紀では素戔男尊、素戔嗚尊、古事記では建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと、たてはやすさのおのみこと)、須佐乃袁尊
呼び名は変わるようです。

二つ目の鳥居です。立て方にも決まりがあるのでしょうか。
参拝者はひとりも居らず、静寂でしたが、やはり歴史は感じました。
2礼2拍手1礼で参拝を済ませました。
本殿の脇に舞台があります。
お神楽舞で使うのでしょう。
元日には大勢の参拝がある事と思います。
戦後の歴史教育では記紀を教えなくなっていますが、この御祭神の名を知っていました。
昔確か唱歌で「村祭り」と言う歌がありました。
村の鎮守の神様の
今日はめでたい御祭日
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
朝から聞こえる笛太鼓
年も豊年満作で
村は総出の大祭
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
夜までにぎわう宮の森
治まる御代に神様の
めぐみ仰ぐや村祭
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
ドンドンヒャララ ドンヒャララ
聞いても心が勇み立つ
歌詞を読むと、神社は村のしくみの中心に座した大切な存在だったと思います。
神の恵みに対して歌詞に感謝の念が溢れ出ています。
鎮守:一定の地域に住んでいる人を守護している神。
氏神:遠い先祖の神、いわゆる遠つ御祖(みおや)の神。
産土:自分の出生地や、祖先の地に対して、特別の思い入れとか、出自意識をもって、その土地の神が自分の運命を左右しているものとして信仰する神。
参考資料




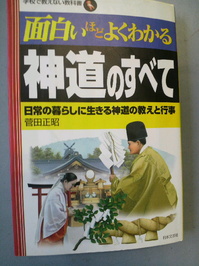
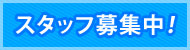
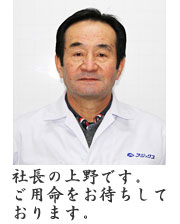



コメントを残す